家事をしない夫の離婚率が高いのは当然です。

まぁ・・・そうね
我が家は結婚20年目にして、妻である私から「離婚を前提にした別居」を切り出しました。

限界だった・・・
20年一緒にいて今さら?と思う人もいるかもしれませんが、厚生労働省が毎年公表している「令和4年人口動態統計(確定数)の概況」では、離婚した約18万組の夫婦のうち、もっとも多い同居期間は「5年未満」そして、次に多いのが「20年以上」の熟年離婚となっています。
私は、自分のタイミングで「いつでも離婚できるように」お金の整理から始めています。
家事をしない夫は離婚率が高い?20年連れ添った妻が見た“本当の理由”
家事をしない夫は本当に離婚率が高いのでしょうか?実は、「家事をしない」という行動の奥には、もっと根深い問題が潜んでいます。
- 統計から見る熟年離婚と家事分担の関係
- なぜ“家事をしてるつもり”の夫が妻を追い詰めるのか
- 家事をしてくれてもモヤモヤが消えない理由
それではまず、統計の視点からこの問題をひも解いていきましょう。
統計から見る熟年離婚と家事分担の関係
「夫が家事をしない」という問題が、実際に離婚率にどう影響しているのか。これを考えるためには、まず統計データを見てみる必要があります。
厚生労働省の発表した「令和5年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2023年の離婚件数は約18万4千組。その中で、特に多かったのが『同居期間5年未満の離婚』と『20年以上の熟年離婚』という2つの層です。

知らなかった!

うちは離婚したら熟年離婚だ・・・
このデータは、結婚してすぐに夫婦生活が破綻するケースと、長年我慢した結果として離婚を選ぶケースが共に多いことを意味しています。
| 同居期間 | 離婚件数 |
|---|---|
| 5年未満 | 約5.3万組 |
| 20年以上 | 約4万組 |
特に「20年以上の夫婦」の離婚が多い背景には、家事や育児の分担が偏ったまま何十年も過ぎ、「もう限界」と感じてしまう妻の存在があります。
内閣府の『令和元年度 家事と仕事のバランスに関する調査』によると、共働き家庭においても家事の7割以上を妻が担っているという結果が出ています。さらに、育児に関しても、夫の参加率は4割未満にとどまっているのが現状です。
つまり、「家事をしない夫」という問題は、実際に多くの家庭で不満やストレスの原因となっており、それが離婚率の高さにつながっていると考えられるのです。
私自身も、20年以上連れ添った夫との生活の中で、家事に関して何度も話し合いを繰り返してきました。でも、改善されることなく・・・それが積もり積もって、最終的に「別居」という選択肢を選んだ一人です。
数字は冷静ですが、その裏には「限界まで頑張ってきた誰かの人生」があることを、忘れてはいけませんね。
次は、「家事をしてるつもり」の夫が、なぜ妻をさらに追い詰めてしまうのか?について考えていきましょう。
なぜ“家事をしてるつもり”の夫が妻を追い詰めるのか
家事を「まったくやらない夫」よりも、実は「自分ではやっているつもりの夫」のほうが、妻を精神的に追い詰めてしまうケースが少なくありません。
「料理は作ったよ」「オムツ替えたよ」「ゴミ出したよ」――そんな風に“実績アピール”をされても、妻の心はなぜか晴れない。それどころか、モヤモヤが積もっていくばかり。

やってくれるだけマシと自分に言い聞かせてみてもモヤモヤ・・・
私自身も、夫から「手伝ってるじゃん」と言われるたびに、言いようのない虚しさを感じていました。
それは、単に「やった・やらない」の問題ではないんです。
たとえば、料理を作ってくれても、片付けはしない。洗濯を回してくれても、干してはくれず・・・濡れた洗濯物が、洗濯機のなかに一晩じゅう入っていたなんてことも数え切れません。
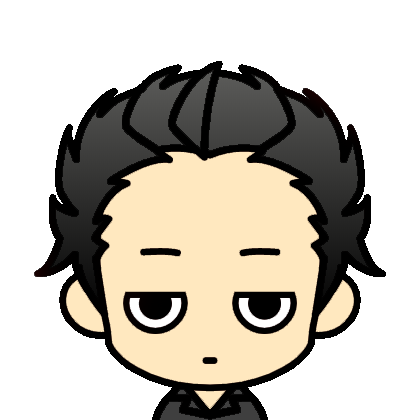
・・・・・。
“家事の全体像”ではなく、“作業の一部分”だけを切り取って評価しているんですよね。
こうした「部分的な家事」が積み重なると、妻の「気づかれない負担」だけがどんどん増えていくんです。
だって、考えてみてください。濡れたままの洗濯物が一晩、洗濯機の中にあったら…開けた瞬間「またか!干せないなら洗わないでよ・・・」とさえ思ってしまいます。生乾き臭のするシワシワの洗濯物をもう一度洗うときの気の滅入りようは、ただの洗濯の何倍も疲れます。

イラつく・・・
心理学の分野では、こうした状態を「感情的な労働(エモーショナル・レイバー)」とも呼びます。
つまり、目に見える作業以上に、段取り・先回り・気配りといった「見えない家事」が女性に偏っている状態です。
にもかかわらず、「俺もやってる!」という自己満足だけが前に出てくると、妻の中では“理解されていないこと”そのものが最大のストレスになるんですよね。
まるで、自分の努力も、疲れも、誰にも気づいてもらえないような孤独感。
夫は「やってるつもり」、妻は「なんか違う・・・」――このすれ違いのギャップこそが、信頼や愛情をすり減らしてしまう最大の原因かもしれません。
この章を読んで、「うちもそうかも…」と感じた方。安心してください。あなたが繊細すぎるわけではありません。誰にでも起こりうる問題なんです。
次の章では、そんな見えないストレスが、なぜ「家事してくれてるのにモヤモヤが消えない」状態を生むのか、もう少し深く掘り下げてみましょう。
家事をしてくれてもモヤモヤが消えない理由
夫が家事をやってくれている。なのに、なぜか心の中にはずっとモヤモヤが残る。
これは多くの妻が抱える感情であり、私自身も何度も感じたことです。
「お皿洗ってくれて助かったよ」と思う一方で、「なぜかぽつんと残っているフライパン」「スポンジは生ゴミの横に放置」「ふとテーブルを見ると下げてない食器」――結局、“あと始末”や“片付け直し”は全部こっち。
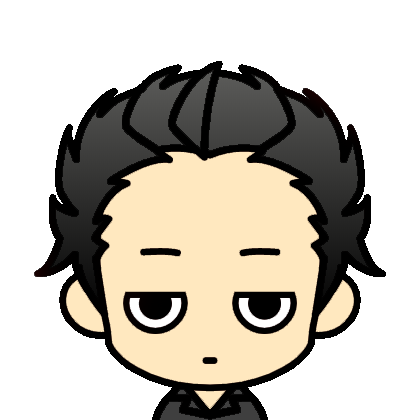
文句ばっかり!出来る限りのことはしてるだろ!

・・・!!
こういう小さなことの積み重ねが、「もういい、私がやるから」と自己犠牲モードに入りやすくなる原因
でもこの「やってくれたことへの感謝」と「やっぱり負担が減らない」という矛盾した気持ちが、実は一番苦しい。
本当は嬉しい。やってくれるのはありがたい。だけど、“どこか違う”――やってくれたと思うと毎回、文句を言うのもなんだか違うようで・・・この微妙なズレが、どんどん心を疲れさせていくのです。
なぜこんなにしんどくなるのか。実は、妻が家事に求めているのは「作業の代行」ではなく「一緒に家庭を支えているという安心感」なんです。
つまり、「一緒にやってる」という気持ちの共有がないまま、作業だけされても、“心の孤独感”はまったく埋まらないということ。
この孤独こそが、夫婦関係を壊す最大の要因になります。
とくに、出産・育児期やフルタイム勤務のタイミングでは、身体的にも精神的にも余裕がなく、たった一言「大丈夫?」「ありがとう」だけで救われることがあったりしますよね。
でも、そういう言葉すらなく、作業だけが“やったアピール”で積み上がっていくと、妻の気持ちは「共に暮らしてるのに、心はひとり」になってしまう。
これはもう、家事をしてくれている・くれていない以前の問題。
“心を支えてくれていない”ことが、最大のストレスになっているのです。
「ちゃんとやってるつもりの夫」と「心が折れそうな妻」――このすれ違いが、長年続いたときに、夫婦関係が静かに崩れていく。
次の章では、私自身の結婚生活で訪れた、離婚を考えた3つのターニングポイントについてお話します。
離婚を考えるようになった3つのターニングポイント
結婚生活が長くなる中で、私が「離婚」を現実的に考えるようになった出来事がいくつかありました。
- 産後すぐの孤独と、寄り添わない夫
- 共働きでも“名ばかり分担”の現実
- 子育てが落ち着いたあとに訪れる“虚しさ”
まず最初のターニングポイントは、出産直後の時期でした。
産後すぐの孤独と、寄り添わない夫
出産後、毎日が必死でした。睡眠はほとんどとれず、授乳、オムツ替え、抱っこ、泣き声…。体力も気力もすり減って、「今日一日を乗り切れるか」それだけが目の前の課題でした。
ママだって、おっぱいの出ないパパに「授乳して」と言っているわけではありません。

パパのおっぱい・・・

むしろ嫌・・・
2~3時間おきの授乳で、まとまった睡眠時間がとれないのは確かに辛いですよね。
でも、私は眠れないことより、暗い中、1人で何回も起きて授乳している寂しさのほうが辛かったです。
毎回じゃなくていいし、毎日じゃなくていい・・・本当にたまにでもいいから、一緒に起きて授乳の間に他愛もない話をしたり、「大変だね」って笑い合ったりできたら、それで良かった。
察してくれなんて言っていません。正直に伝えたんです。
にも関わらず、横でいびきをかいて寝ている旦那を見て涙がこぼれてきました。
「一人じゃない」「私には、この人がいる」そういう信頼と安心感をママは求めています。少なくとも私は、ずっとそれだけを求めていました。

わかる・・・
夫は決して冷たい人ではありませんでした。仕事が忙しいのも分かっていましたし、オムツ替えやお風呂も“手伝って”くれることもありました。
でも、一番欲しかったのはその場限りの“手伝い”じゃなくて、“気持ちに寄り添ってくれること”だったんです。

それだけでよかったのに・・・
実際、産後クライシスという言葉があるように、出産直後の夫婦関係はとても壊れやすいもの。
とくに、女性はホルモンバランスの乱れや心身の変化によって、心が敏感になっている時期でもあります。
そんな時に、夫から「俺も疲れてるんだよ」と言われてしまうと、“自分のしんどさを受け止めてもらえない絶望感”に襲われます。
これは実際、私が味わった感情です。
「私ばっかり頑張ってる」「一人で子どもを育ててるみたい」――そう思い始めたとき、夫婦の心の距離は、確実に開き始めていたのだと思います。

思い出したら今でも泣ける・・・
出産は、夫婦にとって一大イベントのはず。でも、現実はママだけが命を削り、パパは“その場にいるだけ”になっている家庭も少なくありません。
そしてこの「最初のすれ違い」が、その後何年も尾を引く“根の深いわだかまり”になっていくのです。
次の章では、共働きになってから感じた「分担しているはずなのに、結局私ばかり」という現実をお話しします。
共働きでも“名ばかり分担”の現実
夫と話し合って、家事は分担しているはずなのに。
フルタイムで働きながら、子どもの送り迎え、夕飯の支度、洗濯、片付け、明日の準備……。一日の終わりには、「結局、私が全部やってるじゃない」と思ってしまうこと、ありませんか?
私も、共働きである以上、家事も育児も“二人でやるもの”だと思っていました。

当然でしょ!
話し合いもしました。「これとこれはあなたがやってね」と決めて、納得してスタートしたはず。
なのに、「忙しいから今日は無理」「あとでやる」――そして、その“あとで”が永遠に来ない。

ムキーーーーーー!!
分担したはずの家事が、知らない間に全部私の担当になっていたんです。
そして、一度も「ごめんね」「代わりにやってくれてありがとう」とは言われなかった。
家事というのは、“自分がやらないと誰もやらない”という状況が続くと、無言のストレスが溜まっていくんですよね。
しかも、夫は「俺だってやってる」「得意なことはやってる」と主張するけれど、“都合のいい部分だけ切り取って家事してる感”を出されても、全体のバランスが取れてないから、逆にイライラしてしまう。
調査でも、共働き家庭でも女性が7割以上の家事を担っているという結果が出ています(内閣府・令和元年度 家事等と仕事のバランスに関する調査)。
これはもう、私たちだけの問題じゃない。“構造”として偏ってしまっているんです。
でも、日常はそんな社会のせいにしても変わらない。だからこそ、夫との間でバランスを取ろうと、何度も何度も「やってほしい」と伝えてきました。
だけど、気づけば「お願い→やらない→我慢→爆発→謝罪→元通り」のループ。
もう、このやりとりに心がすり減ってしまったんです。
共働きなのに、家庭の負担は片方だけ。この不公平感は、信頼をすり減らす大きな要因になります。

役割分担したはずなのに・・・
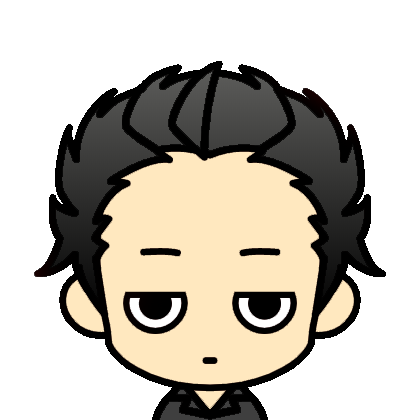
できることはやってる・・・
次の章では、子育てが一段落してから感じた「このままでいいのか…」という虚しさについて、お話しします。
子育てが落ち着いたあとに訪れる“虚しさ”
子どもがある程度成長して、手がかからなくなってきた頃。
ふと、自分の人生を立ち止まって見つめたとき、胸の奥に湧いてきたのは「虚しさ」でした。
これまで、ずっとずっと、子どものために、家族のために、がむしゃらに頑張ってきました。それが、幸せにつながっていると信じていたんです。
でも、いざ子どもが少しずつ手を離れ、自分の時間が持てるようになったとき、「このままこの人と、あと何十年一緒に暮らすのか…?」という不安がよぎったんです。
家事も育児も仕事も、ずっと自分が中心で回してきた毎日。
その中で、何度も「疲れた」「助けて」と言ったのに、心から寄り添ってくれることは少なくて。
気づけば、夫婦でいるのに、心はずっと一人ぼっちだった気がします。

ひとりより寂しい
「もう少し頑張れば変わるかもしれない」
「私が我慢すれば、家族は壊れない」
そんな風に、いつの間にか“自分を納得させる言い訳”を積み重ねて、時間だけが過ぎていきました。
でも、ふとした瞬間に思うんです。
「この人と一緒に老後を迎えたとき、私は幸せなんだろうか?」
子どもの手が離れた今だからこそ、自分の人生に向き合う時間ができたのかもしれません。
熟年離婚が増えている背景には、こうした「夫婦としてではなく、人として尊重されてこなかった日々」に気づく瞬間があるのだと思います。
ずっと“家族のため”に頑張ってきたママだからこそ、自分の幸せを考えてもいい。

いいの?

いいんだよ。
「あと30年、40年…このままでいいの?」と心に浮かんだその想いは、人生を見直す大切なサインかもしれません。
もし、私と同じように「離婚」の二文字が目の前にあるならこちらの記事も参考にしてください。
関連記事:離婚のお金が不安で動けない人へ|費用・生活費・養育費のリアルと準備法
次の章では、夫が“なぜ家事をしないのか”を心理的な視点から掘り下げていきます。
家事をしない夫とどう向き合う?3つの視点から考える選択肢
ここまでお読みいただいて、「もう限界かも」と感じた方も多いかもしれません。
でも、一方で「まだ諦めたくない」「どうにか改善したい」という気持ちも、心のどこかにあるのではないでしょうか。
この章では、感情だけでなく、冷静な視点で“夫とどう向き合うか”を一緒に考えてみましょう。
- 男性側の心理と“やらない理由”を理解する
- 話し合っても変わらない夫にどう対応するか
- 「変えられるのは自分だけ」と気づいたときにすべきこと
まずは、夫がなぜ家事をしないのか、心理的な背景を探ってみます。
男性側の心理と“やらない理由”を理解する
「家事をしない夫」と聞くと、「怠けてるだけ」「思いやりがない」と感じてしまうのは当然です。
でも、少し視点を変えてみると、夫自身にも“できない理由”や“無意識の抵抗”があることが見えてきます。
たとえば、昔ながらの「男は外で働き、女は家を守る」という価値観の中で育った男性は、“家事=女性の仕事”という先入観を無意識に持っていることがあります。
また、家事スキルに自信がないというケースも意外と多いです。
「やってみたけど怒られた」「自分のやり方じゃ通用しない」――そんな経験をした夫は、“自信をなくして家事から距離を置く”という心理に陥りがちです。
さらに、感情を言語化するのが苦手な男性は、「何をどう改善すればいいのか分からない」まま、なんとなくやらなくなることも。
つまり、“やらない”のではなく、“やれない・やり方が分からない・どう接していいか分からない”というケースも多いんです。
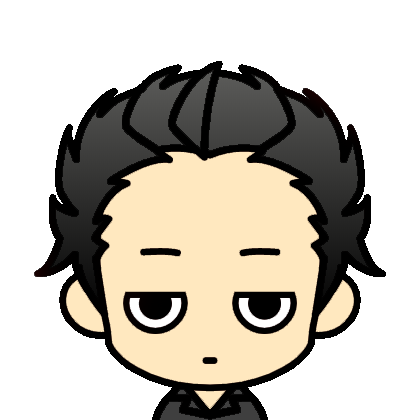
そ・・・そうなのだ!

だまれ!!!
もちろん、これは言い訳にはなりません。家族はチーム。どちらか一方に負担が偏るのはおかしいです。
でも、相手を変えたいなら、まず「なぜできていないのか?」を知ることはすごく大事な視点だと思います。
私自身、夫と何度もぶつかってきましたが、夫にも「苦手意識」「どうしていいか分からない不安」があったことに、あとから気づきました。
そして、「教えてあげる」ではなく「一緒に覚えよう」というスタンスに変えたとき、夫の態度にも小さな変化が生まれたんです。
変わらない夫を責め続けるよりも、まずは「なぜそうなのか?」に目を向けることで、夫婦の会話は少しだけ柔らかくなります。
▼こちらの記事は、実際にパパひらめが書いた「言い訳」です
関連記事:子育てをしないと非難を受けているパパの言い訳を聞いて貰おうと思う
次の章では、それでも変わらない夫と向き合う方法を考えていきます。
話し合っても変わらない夫にどう対応するか
「何度も話し合ったのに、結局変わらない。」
そんな状況に、心が折れかけている方も多いのではないでしょうか。
私もそうでした。冷静に伝えたつもりがスルーされたり、逆ギレされたり。

言葉が届いてる感じがしない・・・
何度も期待して、何度も裏切られて、気づけば「話すこと自体が疲れる」ようになってしまったんです。
でも、そんな時に自分に問いかけたのが、「この関係を続けたいのか、それとも終わらせたいのか?」という問いでした。
もちろん、簡単に答えなんて出ません。

長年連れ添った「情」もあるよね・・・
でも、「変わらない人を無理に変えようとすること」こそが、いちばん心をすり減らす行為なのだと気づいたんです。
では、どう対応すればいいのでしょうか。
答えは、「自分の心を守る方向に舵を切ること」だと思います。
例えば、以下のような方法があります。
- 夫に期待することを一度手放す
- 必要最低限の連絡や会話に絞る
- 自分の時間や趣味を意識的に優先する
- 信頼できる人や第三者に相談する
- 具体的な離婚準備(情報収集・相談)を始める
「諦める」というとネガティブに聞こえるかもしれませんが、実際は「期待しすぎるのをやめる」という、自分を守るための選択です。
そして、もし気持ちが固まりそうなら、離婚について専門家に話を聞いてみるのも一つの手です。
実際に相談したことで、「まだできることがあるかも」と思えた人もいれば、「やっぱり離婚しよう」と前を向けた人もいます。
自分の人生を立て直すために、「話しても変わらない相手」とどう距離を取るか。
それは、家族のためでもあり、なによりあなた自身を大切にする選択でもあるのです。

そろそろ自分を大切にしよう!
次の章では、「夫が変わらないなら、自分をどう変えるか」という視点からの向き合い方を見ていきましょう。
「変えられるのは自分だけ」と気づいたときにすべきこと
夫に何度言っても伝わらない。
優しく言っても、怒っても、泣いても、何も変わらない。
そのたびに、期待して、傷ついて、また我慢して……。

努力が報われないこともあるって知った
そんなループの中で、ふと気づいたんです。
「あ、私、ずっと“他人を変えよう”としてたんだな」って。
だけど、どれだけ頑張っても、変えられるのは自分だけ。
その事実を受け入れたとき、少しだけ心が軽くなりました。
もちろん最初は虚しさもありました。「こんなに頑張ったのに…」という悔しさもありました。
でもそこから、「じゃあ自分はどうしたい?」という問いに意識が向き始めたんです。
たとえば、こんなことを始めてみました。
- 自分のためだけに時間を使う(趣味・運動・一人の時間)
- 「もう無理」と感じたときは、相手に不満を言うよりもまず自分を労わる
- 心の整理をするために、日記やメモに気持ちを書く
- 女性支援センターやFP、カウンセラーなど第三者の手を借りる
どれもすぐに劇的に変わるものではありません。
でも、「私には選択肢がある」「私は変われる」という感覚を取り戻せたことが、何より大きな一歩でした。
人は、“何も変えられない”と思ったときに最も苦しくなるんです。
だからこそ、「自分を変える」という方向に意識を向けるだけでも、少しずつ心の風通しが良くなっていく気がします。
夫を変えようとするのをやめるということは、いい意味で「期待しない」「諦める」ということ。諦めた先で「まあ、いいか」と思えれば一緒にいればいいし、「無理だな」と思ったら別々の道を歩むことを考えればいいんです。

相手ありきの幸せじゃなく自分で自分を幸せにするんだ!
この先どうするかは、まだ分からない。だけど、「自分はどう生きたいか」を考え始めた今、少しずつ未来が見える気がするのです。
次の章では、離婚前に試してみる価値ありの「新しい夫婦の形」をご紹介します。
50代からの夫婦関係に見える“新しい選択肢”
子育てが終わり、夫婦二人の生活に戻ったとき。 20年、30年の積み重ねで「家事をしない夫」に対するモヤモヤは、むしろ以前より強く感じられることもあります。 一方で、この年代だからこそ「離婚する/しない」以外の新しい選択肢を考える人も増えています。
卒婚・別居婚という柔らかな距離の取り方
「卒婚」という言葉が広がってきたように、同居しながらも生活スタイルをあえて分け、籍はそのままで生活を別にする夫婦も増えています。 また、互いの自由を尊重する「別居婚」の形もあります。 離婚だけが答えではなく、距離の取り方を工夫することで心の負担を減らすことができます。
自分の楽しみや時間を増やす
夫に変わってもらうのを待つよりも、自分の時間や楽しみを増やすことに意識を向ける。 趣味を始めたり、友人と旅行に出かけたりすることで、ストレスを和らげられます。 「夫は夫、自分は自分」と考えるほうが、気持ちも軽くなります。

文句ばかりだと自分も疲れちゃうよね!
お金の安心が夫婦関係を支える
「離婚したいけれど生活が不安でできない」…50代ではこう感じる人も少なくありません。 老後資金や年金、退職金の見通しが立つと、「一緒に暮らしながら文句を言いつつやり過ごす」という選択肢も前向きにとれるようになります。
実際に、以下のようなファイナンシャルプランナー相談を活用して安心を得る人も多いです。
結婚生活に正解はひとつではありません。 「どうしても離婚しかない」と思う前に、生活やお金の工夫を取り入れて、これからの人生を少しでも心地よく過ごす方法を探してみませんか?
次の章では、離婚を考える前にやっておくべき準備について、具体的にお伝えします。
離婚を選ぶ前にしておくべき5つの準備
「離婚するかどうかはまだ分からないけど、いざというときのために備えておきたい」
そんな気持ちが芽生えたときに、やっておくべき準備があります。

これ、すっごい大事!
感情だけで動くと、後で「もっと早く調べておけばよかった…」と後悔するケースも少なくありません。
この章では、離婚を決断する前にやっておくと安心な5つの具体的な準備をお伝えします。
- 自分の資産・ローン・支出を把握する
- 住まい・仕事・子どもの生活環境を見直す
- 法律や手続きについて最低限の知識を持つ
- 第三者や専門家に相談する
- 離婚後の生活シミュレーションをしておく
まずは、最も現実的で重要な「お金の把握」から始めましょう。
▶顧客満足度95%の保険相談なら保険マンモス① 自分の資産・ローン・支出を把握する
離婚後の生活で最も大きな不安要素は「お金」です。
今は専業主婦やパートでも、いざ一人で生活するとなると、収入・貯金・支出の全体像を把握しておく必要があります。
具体的には、以下のような項目を紙やスマホでメモしておきましょう。
| チェック項目 | 確認方法 |
|---|---|
| 通帳・預金口座の残高 | ネットバンキング、通帳 |
| 夫婦共有の貯金・積立 | 口座名義・契約書を確認 |
| 住宅ローンの名義と残債 | 住宅ローン明細書 |
| 毎月の生活費(固定費・変動費) | 家計簿・クレカ明細 |
| 子どもの教育費・習い事 | 月謝・年間支出を整理 |
離婚時には、財産分与や養育費、住宅の扱いなどお金の話が避けて通れません。
「知らなかった」「相手が全部管理していた」という状態では、不利な条件を飲まざるを得なくなることもあります。
私も、家計を“なんとなく”で把握していた時期がありましたが、離婚を視野に入れたとき初めて「知らなすぎた」と危機感を持ちました。
ポイントは、今すぐに離婚するかどうかに関係なく、「いざというとき慌てない自分」を作っておくことです。
次の章では、住まいや子どもの環境、仕事など「生活基盤の整備」についてお話します。
② 住まい・仕事・子どもの生活環境を見直す
お金の次に大切なのが、「どこで、どう暮らすか」という生活の基盤です。
特に子どもがいる場合、住まい・学校・仕事の3つはセットで考える必要があります。これは小さな子どもだけでなく、高校生・大学生など、ある程度大きくなった子どもがいる家庭にも当てはまります。
離婚後、「子どもは今の学校に通い続けられるのか?」「引っ越すなら通学手段は?」「自分の仕事はどうする?」など、現実的な課題が一気に押し寄せてきます。
たとえば、子どもと一緒に暮らす場合、 ある年齢以上になれば一人部屋を用意する必要が出てきたり、家賃や光熱費が上がったりと、 “家の広さ”や“間取り”も考慮するポイントになります。
一方で、子どもが一人暮らしを始めるなら、仕送りや家賃補助など、 親の支出バランスが大きく変わってきます。
そのためにも、離婚を考え始めた段階で、次のようなことを一つずつ整理しておくことが大切です。
- 現在の家を出るか、住み続けるかの選択
- 引っ越しが必要な場合、家賃相場・転校の影響を調べる
- 職場や働き方(時短・パート・正社員)の再検討
- 子どもの学校・保育園との距離や通学手段の確認
- 大学生などであれば、同居するか・一人暮らしするか
- 祖父母・親戚・友人など、サポートしてくれる人の有無
たとえば、今の家に住み続けたい場合でも、名義が夫であるか、住宅ローンが誰のものかによって状況は大きく変わります。
また、離婚後に働きながら生活を維持するには、 「通勤時間の短さ」「柔軟な働き方」「子どもの生活リズムに合う職場環境」も重要なカギになります。
子どもが大学生や社会人でも、家にいる間は“生活の土台”を支えるのは母であることが多いもの。 無理なく働ける環境を整えることが、長い目で見て家族全体の安定につながります。
子どもにとっても、親が安定して笑っていられることが何よりの安心材料になります。住まいも仕事も、“無理なく続けられる形”を選ぶことがいちばんの優しさです。
今すぐ離婚しなくても、「自立できる環境を整えておく」ことは、心の保険になります。
次の章では、実際に離婚に進む場合に必要な「法律・手続きの知識」についてご紹介します。
③ 法律や手続きについて最低限の知識を持つ
離婚を考えるとき、「法律とか手続きってなんだか難しそう…」と感じる方も多いと思います。
実際、私も「調停って何?」「協議離婚と何が違うの?」「財産分与ってどこまで?」と分からないことだらけでした。
でも、不安の正体って、実は「知らないこと」からくる怖さだったりするんです。
だからこそ、離婚を本格的に進める前に、最低限の法律知識を持っておくことはとても重要です。
ここでは、特に押さえておきたいポイントを簡潔にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離婚の種類 | 協議離婚(話し合い)/調停離婚(家庭裁判所で調整)/裁判離婚(訴訟) |
| 財産分与 | 婚姻中に築いた共有財産は原則50:50で分割対象 |
| 養育費 | 子どもの年齢・人数・相手の収入に応じて金額が決まる |
| 親権 | 離婚時に必ず決定。母親側が多いが絶対ではない |
| 面会交流 | 離婚後も子どもと親が会う権利。拒否はできないケースも |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金を分割する制度(申請が必要) |
上記の情報はあくまで概要です。実際のケースによって内容は変わりますが、ざっくり知っておくだけでも気持ちの準備が全然違います。
また、インターネットだけで調べると情報が偏ったり古かったりするので、できれば弁護士や法テラス、市役所の無料相談などを活用するのがおすすめです。
私自身、法テラス(無料の法律相談)でアドバイスをもらったことで、「今すぐ決めなくても、段階を踏めばいいんだ」と安心できた経験があります。
法的な“正しい知識”は、感情が揺れたときの冷静な支えになります。
次の章では、離婚後の暮らしをイメージするための「生活シミュレーション」についてお話します。
④ 第三者や専門家に相談する
離婚を考えている時期って、ものすごく孤独です。
「誰にも言えない」「話しても理解されない」「反対されたらどうしよう」――そんな思いで、ずっとひとりで抱え込んでいませんか?
でも、本当に限界が来る前に、信頼できる“第三者”に話すことはとても大切です。
話すことで、心が整理されたり、「自分は間違ってなかった」と感じられることもあります。
私もそうでした。母親に初めて話したとき、涙が止まらなくて驚きました。
言葉にして初めて、自分がどれだけ我慢していたか、気づけたんです。
そして、その後は専門家にも相談しました。
以下は、実際に利用できる相談先の一例です。
| 相談先 | 特徴・内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 市区町村の女性相談窓口 | 離婚・DV・育児などの相談が可能。弁護士の無料相談を実施している自治体も | 無料 |
| 法テラス | 法律の基礎知識・弁護士紹介・費用の立て替え制度も | 無料〜低額 |
| ファイナンシャルプランナー(FP) | 離婚後の生活設計やお金の整理に特化。女性FPも増えています | 保険のマンモスなら無料 |
| カウンセラー・心理士 | メンタル面の整理や、感情のコントロール、自己肯定感の回復に有効 | 5,000円前後(自治体によっては無料) |

私はお金の不安が大きかったからFP(ファイナンシャルプランナー)に相談したよ♪保険のマンモスは登録しているFPさんが多いから悩みに合わせて、その分野に詳しいFPさんを紹介してくれるよ!
大切なのは、一人で全部決めなくてもいいということ。
「話すだけでスッキリした」「選択肢が広がった」と感じる方は本当に多いです。
周りに言いにくいときは、匿名で相談できる窓口やチャット相談もあります。
「私は弱い」と思わないでください。
相談することは、“逃げ”ではなく“準備”です。
あなたの人生をあなた自身の力で守るために、専門家の知識や経験を頼ることは、とても賢い選択です。
次の章では、離婚後の生活をリアルに想像するための「生活シミュレーション」の方法をご紹介します。
⑤ 離婚後の生活シミュレーションをしておく
離婚を現実的に考え始めたら、「離婚後の生活」を具体的にイメージすることがとても大切です。
「なんとかなるでしょ!」では済まないのが現実。特に子どもがいる場合、生活費・住居・働き方・支援制度などをきちんと考えておく必要があります。
以下のような項目を、一度紙に書き出してみると整理しやすくなります。
| 生活シミュレーション項目 | 確認方法・目安 |
|---|---|
| 毎月の収入見込み | 自分の給料・パート収入・養育費・手当 |
| 毎月の支出見込み | 家賃・食費・光熱費・保険・通信・学費など |
| 住まいの確保 | 賃貸の審査条件・初期費用・通勤通学の利便性 |
| 働き方 | 時短勤務・在宅ワーク・再就職・資格取得など |
| 利用できる支援制度 | 児童扶養手当・母子医療・住居手当など(役所で確認) |
これを「シミュレーションした結果、今はまだ難しいな」と思ったなら、離婚を一旦保留にする判断もアリです。
逆に、「意外とやっていけそう」と感じるなら、次の一歩へ進む勇気になるでしょう。
大事なのは、感情だけで動かず、現実をきちんと見据えること。
私も実際、生活費のシミュレーションをしたことで、どんな収入が必要か・どこを節約できるか・何の支援が使えるかが具体的に見えてきました。
最初は不安でいっぱいでも、数字で見えると気持ちが落ち着きます。
また、全国にはひとり親向けの支援制度がたくさんあります。
市区町村の役所で、「離婚を考えていて支援制度について知りたい」と伝えると、相談員が制度を教えてくれたり、パンフレットをもらえたりしますよ。
「離婚してから考える」ではなく、「離婚する前に準備しておく」ことで、未来は大きく変わります。
次の章では、実際に離婚を選んだ人たちの体験談や、その後の気持ちの変化についてご紹介します。
離婚という選択をした女性たちのリアルな声
ここまで読んで、「やっぱり離婚も一つの道かもしれない」と感じている方もいると思います。
とはいえ、離婚って勇気がいりますよね。
でも実際に離婚を選んだ女性たちの中には、「あのとき決断してよかった」と前向きに生きている人たちがたくさんいます。
ここでは、離婚後のリアルな声をいくつかご紹介します。
◆40代・2児の母/専業主婦 → パート勤務
結婚して15年。家事も育児も一人でこなしてきたけど、もう限界でした。
離婚後は本当に大変だったけど、「自分の人生を取り戻した」という感覚が強いです。
子どもたちとも前より深く向き合えるようになり、今は小さな幸せを感じながら暮らしています。
◆30代・フルタイム勤務/小学生の子ども1人
離婚前は、夫との冷戦状態が続いていて、家庭の空気が最悪でした。
離婚後は精神的にスッと楽になり、子どもも明るくなったと先生に言われました。
やっていけるか不安もあったけど、案外なんとかなります。
◆50代・子ども独立後の熟年離婚
子育てが終わってふと振り返ったとき、「この人と老後を過ごす自分」が想像できませんでした。
最初は世間体や孤独が怖かったけど、今は自由に生きてる実感があります。
もっと早く動いていれば、という気持ちも正直あります。
離婚をした女性たちが口を揃えて言うのは、「もっと自分を大切にしてよかった」という言葉。
決断には時間がかかってもいい。
でも、“自分を犠牲にし続ける人生”が当たり前ではないと気づくだけでも、人生は少しずつ動き出します。
最後に、この記事のまとめと、あなたへのメッセージをお伝えします。
離婚するかどうか迷ったら、“自分を大切にする選択”を
家事をしない夫にイライラして、何度も話し合って、それでも変わらなくて。
心がすり減って、ふと「このままでいいのかな…?」と思うこと、ありますよね。
この記事では、そんなあなたのために、離婚という選択肢の現実と、そこに至るまでの心の動きを一緒に見てきました。
- 夫が家事をしない背景には、価値観や心理的要因があること
- 話し合っても変わらないとき、自分の心を守ることが大事なこと
- 変えられるのは自分だけ。だからこそ、自分の人生を考えていいこと
- 離婚を視野に入れるなら、お金・住まい・法律・専門家への相談など準備が必要なこと
- 離婚後も前向きに生きている人がたくさんいること
何より伝えたいのは、「離婚する・しない」どちらが正しいということはないということ。
大切なのは、「あなたが、あなた自身をどう扱うか」です。
我慢し続けて苦しくなっているなら、「変わりたい」と思う気持ちは、あなたの心からのSOSかもしれません。
今すぐ答えを出す必要はありません。
でも、考え始めたこと自体が、人生を変える第一歩になるはずです。
どうか、自分の人生に正直に。
あなたが、あなたらしく生きられる選択を、心から応援しています。
\信頼の証!お申込み累計57万件超え/
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。
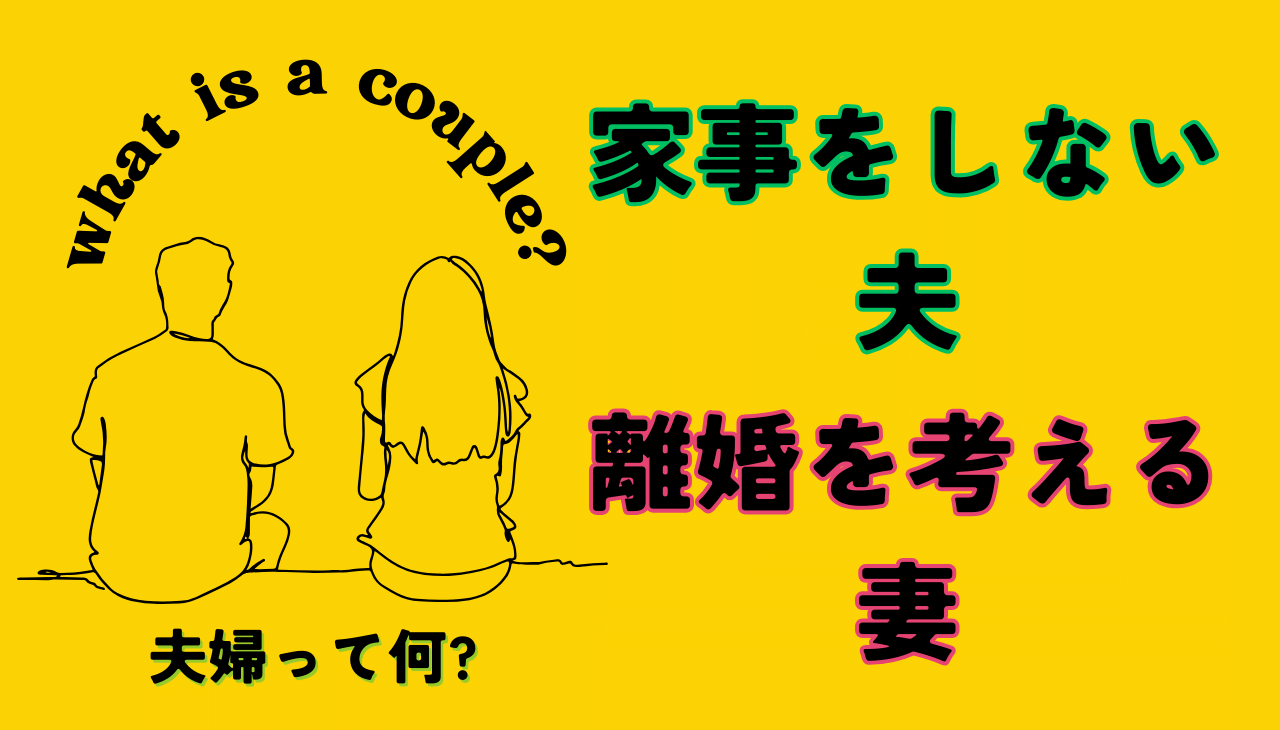
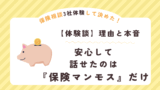


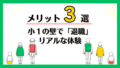

コメント