「うちの子に限って・・・」
なんて、昭和の母親のような言葉を久しぶりに聞きました。というか、僕からすると「どう考えても、あなたの子っぽいよ」と思うのですが、そんな空気を読まない発言をすると、まるで僕が、まるで共感できないゲスな人間であるかのように、その母親に罵詈雑言を浴びせられ、僕の豆腐のようなメンタルが脆くも崩れ去り、立ち直れなくなりそうだったので、「あー、そうなんすねー」と空返事で返しました。

・・・何か、冷たくない?
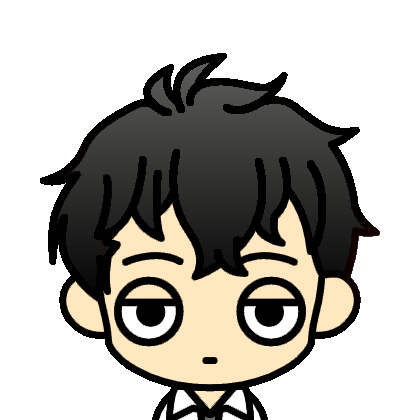
だって・・・
ちなみに、その母親はまるで「子供に裏切られた」みたいな口調でしたが、僕的には、お前の愛情が薄い・・・もしくは、子供の性能以上の期待を掛けているから、裏切られた気になるんだと思うんです。つまり、全ては、母親として、子供への接し方が悪い癖に、あたかも「自分は被害者である」と悲劇の主人公を演じていることが、僕の怒りを助長し、共感もできないし、どちらかというと虫唾が走るのです。

・・・ゲスじゃん?
もちろん、我が家の子育てが正解かどうかは分かりませんが、僕的には、息子たちがヒトの道を外れた場合、僕は最後まで息子に寄り添います。僕が被害者顔することはなく、どちらかというと息子が『ヒトの道』を外れたのは、僕の子育てが間違っていたと認識し、息子の間違いを受け入れ、一緒に償うことを受け入れます。

それはそうか・・・
この記事では無責任に「うちの子に限って・・・」と被害者を装い、まるで悲劇のヒロインのように同情を買おうとする母親の心理について考察していこうと思います。
「うちの子に限って・・・」と思う心理
この言葉を口にする親の心理状態は実に複雑です。表面上は子どもへの信頼を表明しているようで、実は様々な感情が絡み合っているのです。

どういうこと?
まず第一に、これは「自己防衛」の表れと言えるでしょう。自分の子どもが問題を起こしたという事実は、親としての自分自身の評価にも関わってくるからです。「うちの子に限って」と言うことで、子どもの行動と自分の子育てとの因果関係を切り離そうとしているのです。
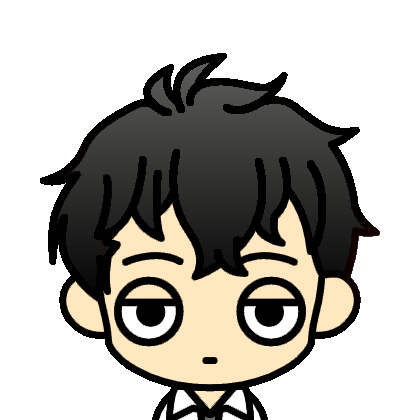
親の責任だよ
次に「理想と現実のギャップ」からくる戸惑いがあります。多くの親は子どもに対して理想像を抱いています。しかし、子どもは親の期待通りには育ちません。その落差に直面したとき、現実を受け入れるよりも「例外的な出来事だ」と否定する方が精神的に楽なのです。

・・・確かに
また、「社会的体裁」への配慮も大きいでしょう。子どもの問題行動は、周囲からの評価に直結します。「うちの子に限って」という言葉は、社会的体面を保つための防波堤となるわけです。
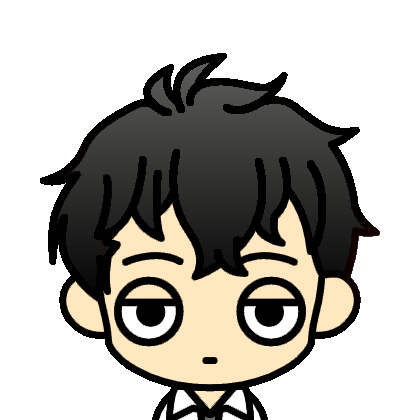
逃げるな・・・
親の期待と子どもの現実
子どもへの期待は親心の自然な表れですが、それが過剰になると子どもにとって重荷になります。僕が出会ったその母親のように、子どもに裏切られたと感じるのは、実は不当な期待を押し付けていた証拠かもしれません。
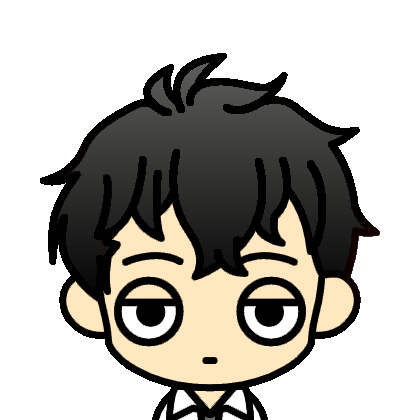
子供の人格を認めよう
子どもは親の分身ではなく、一人の独立した人格を持つ存在です。親の描いた青写真通りに成長するわけではありません。むしろ、親の期待に応えようとして無理をし、結果的に破綻するケースも少なくありません。

そうだね・・・
「うちの子がそんなことをするはずがない」と思う親の背景には、子どもを自分の思い通りにコントロールできる存在だと無意識に考えている節があります。しかし、子どもは親の所有物ではなく、独自の意思と選択肢を持つ個人なのです。
「被害者意識」がもたらす悪影響
親が「子どもに裏切られた被害者」を演じると、子どもとの関係に深刻な亀裂が生じます。子どもは二重の負担を強いられることになるからです。一つは自分の問題行動への対処、もう一つは親の感情を修復するという負担です。

そうだね・・・
このような親子関係では、子どもは本音を打ち明けることができなくなります。親が「被害者」になってしまうことを恐れて、問題を隠すようになるでしょう。結果的に、親子の信頼関係は崩壊の一途をたどります。
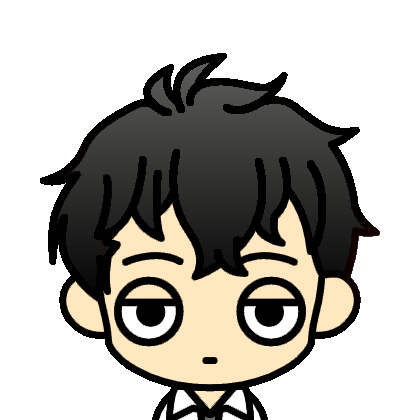
子供が可哀想だよ
さらに悪いことに、親の被害者意識は子どもの自己肯定感を著しく低下させます。「自分は親を傷つける悪い子だ」という自己認識が強化され、健全な人格形成が阻害されるのです。
責任ある親の姿勢とは
子どもが問題を起こしたとき、責任ある親はどう対応すべきでしょうか。僕が考える理想の姿勢は、前文で触れたように「寄り添う」ことです。
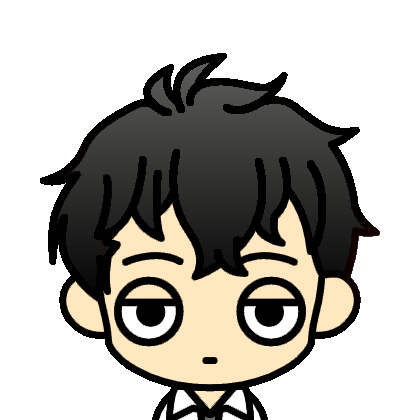
親の役目だと思う
子どもが非行に走ったり、社会的な問題を起こしたりしたとき、それを単に子ども個人の問題と切り捨てるのではなく、親子の関係性や環境も含めた複合的な問題として捉える必要があります。つまり、親も責任の一端を担い、子どもと共にその問題に向き合うということです。

そう・・・ね
「うちの子に限って」と言って現実から目を背けるのではなく、「これが今の我が子の現実だ」と受け止めることが第一歩です。そして、「なぜこうなったのか」を子どもと一緒に考え、解決の道を模索することが重要です。
共感と理解の大切さ
子どもの行動を理解しようとする姿勢は、親子関係の基盤となります。「うちの子に限って」と言って子どもの行動を否定するのではなく、その行動の背景にある感情や状況を理解しようとする姿勢が大切です。
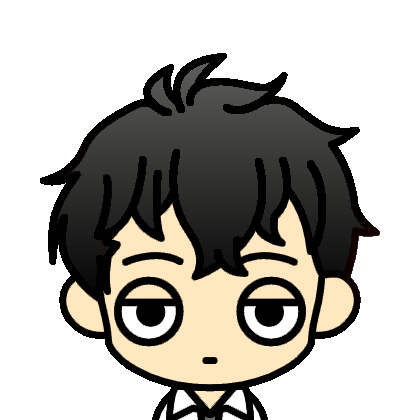
否定は誰にでも出来る
例えば、子どもが万引きをしたとしましょう。それを単に「悪いこと」として叱るだけでなく、なぜそのような行動に至ったのかを理解しようとする姿勢が必要です。もしかすると、友人関係でのプレッシャーがあったかもしれませんし、親の関心を引きたかったのかもしれません。
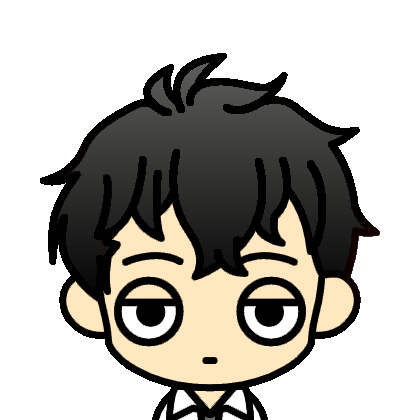
寄り添ってあげる
共感的な理解は、子どもに「あなたは理解されている」というメッセージを送ります。そして、そのメッセージこそが、子どもが自己を肯定し、健全に成長するための土壌となるのです。

そうだね
親子の信頼関係を築くために
最後に、健全な親子関係を築くためのポイントをいくつか挙げておきましょう。
まず、子どもを「自分の延長」ではなく、一人の独立した人格として尊重することです。子どもには子どもの人生があり、その選択を尊重する姿勢が必要です。
次に、子どもの失敗や問題行動を「裏切り」と捉えるのではなく、成長過程の一部として受け止めることです。失敗は学びの機会であり、それを通じて子どもは成長していきます。
また、親自身も完璧ではないことを認め、時には子どもに謝ることも大切です。これにより、子どもは人間の弱さや間違いを受け入れる寛容さを学びます。
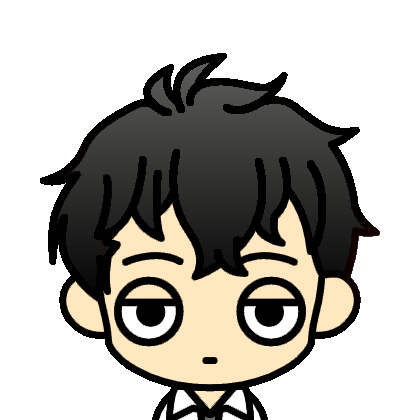
簡単ではないけど・・・
そして何より、無条件の愛情を示すことです。「あなたが何をしても、私はあなたの味方だ」というメッセージが、子どもの心の安全基地となります。

それが親だね
「うちの子に限って」という思考から卒業し、子どもの現実を受け入れることは、親自身の成長でもあります。子どもと共に歩む姿勢こそが、真の親子の絆を育むのではないでしょうか。
おわりに
冒頭の体験から考えさせられたことは多いです。あの母親の言葉に違和感を覚えたのは、おそらく、僕自身が親として大切にしたい価値観と相容れなかったからでしょう。
子育てに絶対的な正解はありません。でも、子どもの人格を尊重し、共に成長する姿勢は間違いではないと信じています。「うちの子に限って」と現実から目を背けるのではなく、「我が子はこういう子だ」と受け入れる勇気を持ちたいものです。
そして最後に、親であることの難しさと素晴らしさを改めて感じます。子どもと向き合い、時には自分自身の価値観や期待を見直すことは容易ではありません。しかし、その過程こそが、親としての成長であり、子どもとの真の絆を深める道なのだと僕は思います。
親も人間です。子育てを通して成長していこうじゃありませんか。
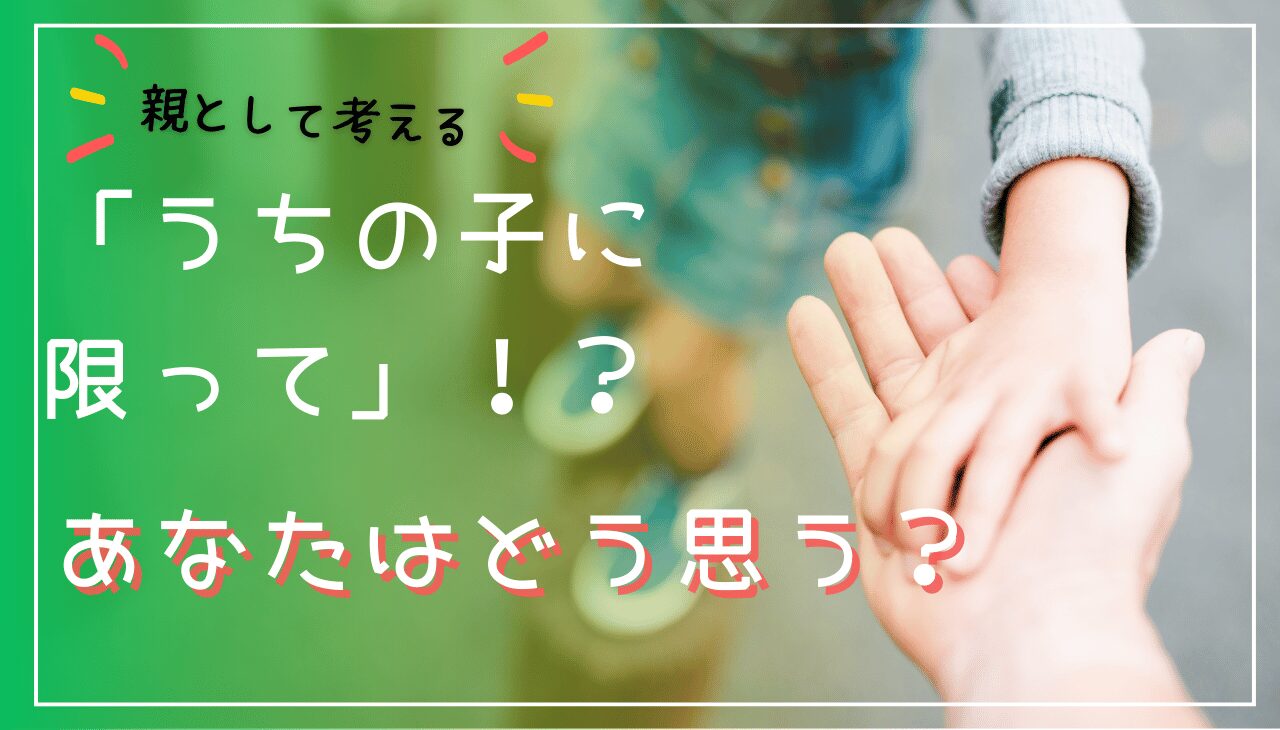

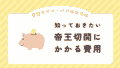
コメント