「もう限界かも…」「このままじゃ壊れてしまう」
そんな思いを抱えながら、ワンオペ育児を必死に頑張っているママはたくさんいます。

もう嫌だ!!
中には、離婚を考えるようになった自分に罪悪感を抱いたり、経済的な不安や世間体を気にして気持ちを押し殺している方もいるかもしれません。

たくさんいそう・・・
この記事では、ワンオペ育児と離婚率の関係性について、実際のデータやリアルな声をもとに深掘りしながら、
・なぜワンオペが離婚に繋がりやすいのか
・離婚しないためにできることはあるのか
・もし離婚を選ぶなら、どんな準備が必要か
といった内容を、同じように悩んだママ目線で丁寧に解説していきます。
この記事を読めば、離婚するにしてもしないにしても、今の苦しい気持ちが少し軽くなるヒントが見つかるはずです。
どうか、一人で抱え込まないでください。
あなたと子どもの人生が、前を向けるように──そんな願いを込めて、書いています。
ワンオペ育児の離婚率は本当に高いの?【事実とデータ】

ワンオペ育児をしていると本当に離婚率が高くなるのか、事実とデータから読み解いていきます。
- ワンオペ育児とはどういう状態か
- なぜワンオペ育児は離婚につながりやすいのか
- 離婚率のデータと年代別の傾向
- 離婚を選ぶ夫婦の共通点とは
- ワンオペが続くと起こる“心の限界”
それでは、順番に解説していきます。
① ワンオペ育児とはどういう状態か
「ワンオペ育児」とは、主に母親が1人で育児・家事のすべてを担っている状態を指します。夫やパートナーが育児に参加せず、物理的・精神的に孤立した育児スタイルです。
もともと「ワンオペ」は飲食業界の「ワンオペレーション(1人で全業務を担当)」から来た言葉で、それが家庭に転用された表現です。つまり、「寝かしつけ」「食事の準備」「オムツ替え」「通院」「保育園対応」「買い物」など、すべてを1人でやっているという状態です。
特に共働き家庭であっても、夫が「仕事が忙しいから」という理由で育児を免除されている場合や、専業主婦であることを理由に育児を押しつけられるケースが多く、実態としては日本の多くの母親がワンオペ状態にあります。
「夫が家にいても育児は全部私」という状態も含めて、ワンオペ育児です。

許せない・・・
身体的な孤独だけでなく、精神的な孤立も含まれるのが特徴です。
ワンオペ育児は、体力の限界、精神的なストレス、不公平感、孤立感など、多くのマイナス要素が蓄積されていくため、夫婦関係の悪化に直結しやすいというリスクがあります。
筆者もかつて「ワンオペ側」だった身として、「これはもうダメかも…限界」と感じた瞬間が何度もあります。だからこそ、まずはこの状態がどういうものかを明確にしておくことが大切です。
② なぜワンオペ育児は離婚につながりやすいのか
ワンオペ育児が離婚につながる理由は、精神的・肉体的・関係性の3つの側面で「積み重なるダメージ」があるからです。
まず精神的には、「私ばっかり頑張っている」「誰も助けてくれない」という孤独感や不満が募ります。これは心のエネルギーを確実に削っていきます。
次に肉体的な問題です。夜泣き、夜間授乳、食事作り、買い物、送り迎えなど、休む暇がありません。慢性的な疲労は、心の余裕を奪い、“相手のことを考える力”さえ感じられなくなってしまうことがあります。
でも、それはあなたの思いやりがなくなったわけではなく、“思いやるほどの余裕がなかっただけ”なんです。
そんな状況で頑張っているあなたを、どうか責めないでください。
そして関係性の問題。夫が育児に関与しない場合、「あなたは家族の一員じゃない」と感じてしまう瞬間が出てきます。ここで信頼や絆が壊れ始め、夫婦関係が冷え切ってしまうのです。
離婚は「突然起こるもの」ではなく、日々の不満や無関心が積み重なって、限界点を迎えた結果です。ワンオペ育児はその引き金として、かなり強力なのです。

本当だよね・・・
「いつもイライラしていた自分が、嫌で仕方なかった」という声は本当によく聞きます。ワンオペは、夫婦の問題だけでなく、自己否定にもつながる深刻な状況なんですよね。

私だってできるなら笑顔で過ごしたい・・・
③ 離婚率のデータと年代別の傾向
では、実際にワンオペ育児と離婚率には相関があるのでしょうか?
厚生労働省「人口動態統計(2023年)」によると、全体の離婚件数は年間約18万件ですが、育児期(0〜5歳)の離婚が圧倒的に多いことが分かっています。
| 子どもの年齢 | 離婚率 |
|---|---|
| 0〜2歳 | 約38% |
| 3〜5歳 | 約20% |
| 6歳以上 | 約42% |
このデータを見ると、子どもが0〜2歳の間に離婚に至るケースが非常に多いのがわかります。これはまさに、ワンオペが最も過酷になる時期と重なっています。
また、内閣府の調査では「離婚理由の上位」に「性格の不一致」「生活態度の不一致」に加えて、「家事・育児の不平等感」が上位に入っており、育児ストレスと離婚の関係が濃いことが裏付けられています。
統計を見ると、決して他人事ではないと感じる方も多いのではないでしょうか。

みんな悩んでいるんだね・・・
④ 離婚を選ぶ夫婦の共通点とは
ワンオペ育児から離婚に至った夫婦には、いくつか共通点があります。
- パートナーが育児・家事に無関心
- 相談しても否定・無視される
- 感情の共有がまったくできない
- 金銭面での不安や不満がある
- 精神的な支えが一切ない
これらのうち、複数に該当すると「自分だけが家族を背負っている」という感覚になります。そして、その不均衡が限界を迎えると、気持ちは「終わり」に向かっていくのです。

全部当てはまってる・・・そんな我が家は家庭内別居中
ちなみに、夫婦の会話頻度が極端に少ないケースも危険信号です。「無言」「あいづちだけ」「事務連絡のみ」の関係は、すでに心が離れている可能性が高いです。
筆者が相談を受けた方も、「夫と何も話してないことに気づいて、自分でも驚いた」とおっしゃっていました。

私のことかな・・・
⑤ ワンオペが続くと起こる“心の限界”
ワンオペ育児のもっとも恐ろしい点は、「限界を超えても誰にも気づかれないこと」です。
ママは頑張り屋さんが多く、「私がやらなきゃ」「母親だから当然」と、無理をしてでも毎日を回そうとします。ですがその代償は、自己否定・感情の抑圧・心のシャットダウンです。
いわゆる「育児うつ」「夫源病(ふげんびょう)」「バーンアウト(燃え尽き症候群)」と呼ばれる状態にまで進行してしまうと、もはや「離婚したい」というより「すべてから逃げたい」という感覚になります。
そして、「この人と一緒にいる限り、私は幸せになれない」と感じると、離婚は選択肢から“出口”になります。
一見すると、離婚は最終手段に見えますが、心の限界に来た人にとっては「唯一の救済」に見えることもあるのです。

うん、分かる・・・
だからこそ、この記事では「離婚も一つの選択肢だけど、限界を迎える前にできることはないか?」という視点で、これからの章をお届けしていきますね。
離婚を考えるママたちの本音とリアルな声
ワンオペ育児で離婚を考えるママたちが、どんな気持ちを抱えているのかをリアルな言葉で紹介していきます。
- 離婚を決意する瞬間あるある
- 「子どものために我慢」は正解なのか
- 離婚後の生活に感じる不安とは
- 離婚経験者のリアルな体験談
感情が揺れるリアルな声を、順番に見ていきましょう。
① 離婚を決意する瞬間あるある
離婚を本気で考えるようになった瞬間には、ママたちそれぞれに「引き金」となる出来事があります。
よく聞かれるのは、次のような場面です。
- 「子どもが高熱でも、夫がスマホゲームをしていた」
- 「産後うつで泣いていたのに、“めんどくさい”と一言で片づけられた」
- 「相談しても、“お前の努力が足りない”と責められた」
- 「“誰のおかげで生活できてると思ってる”と言われた」
- 「土日も寝てばかりで、子どもとの時間を一切持たない」
このような出来事が重なっていくと、「この人とは家族でいる意味がない」「もう、心が死んでる」と感じてしまうのです。
離婚って、派手な喧嘩や事件で決まるのではなく、日々のすれ違いと無関心が“心を冷凍保存”していって、ある日ポキッと折れるように決断されるのです。
離婚を考える人には、「もう感情が動かない」「相手に何も期待していない」という心の終焉のような状態が訪れていることが多いです。

いちばんの味方でいてほしいのに・・・
② 「子どものために我慢」は正解なのか
「子どものために我慢している」という言葉は、多くのママが口にします。
でも、実際には“我慢し続けたその先”に、本当に子どもの幸せがあるのか?というのは、とても深いテーマです。
あるママはこう言いました。「毎日ピリピリしている私を、子どもはびくびくしながら見ていた。それを見て、これが子どものためになるわけないって思ったんです」と。
離婚がすべて正解とは言いませんが、「笑顔のない家庭」「自己犠牲の中で生きる母親」の姿が、子どもに良い影響を与えるかは疑問です。
また、家庭が不安定だと、子どもも精神的に不安を感じやすくなります。逆に、シングルマザーになっても安定した生活・明るい表情を取り戻したことで、子どもも元気になったという例もたくさんあります。
もちろん「我慢すること」も愛ですが、「我慢しないこと」も立派な愛のカタチです。
私はずっと我慢してきましたが、もっと早く区切りをつけたほうが幸せだったんじゃないかと考えることがあります。それは、息子から「夫婦喧嘩を聞いてる時ほど嫌なものはなかった」と言われたから。

ショック・・・でも、そうだよね・・・
「まず自分を大切にすることが、子どもを守ることにつながる」という考えを持ってもよかったと後悔しています。
③ 離婚後の生活に感じる不安とは
離婚を考えるうえで、最大のブレーキになるのが「離婚後の生活への不安」です。
多くのママが口にするのは、次のような不安です。
- 経済的に自立できるのか不安
- 子どもが寂しい思いをするのでは?
- 周囲の目や親族の反応が怖い
- 1人で全部の責任を背負えるか自信がない
- 子どもが「パパに会いたい」と泣いたらどうしよう
これらの不安は、どれもリアルで重たいです。でも、多くのシングルマザーの方が乗り越えている現実でもあります。
今は、児童扶養手当、保育料の免除、住宅手当、就労支援など、公的制度も整ってきています。
また、離婚前に情報収集や準備をすることで、安心して踏み出せるケースもたくさんあります。
「不安を抱えているのは、あなただけじゃない」と伝えたいです。そして「不安は“準備”と“支援”でかなり和らぐ」ということも知ってほしいです。
離婚後にイキイキとした表情を取り戻したママもたくさん見てきました。「あの時決断してよかった」と言う彼女たちを見ていると、未来は悲観するものではないと感じます。
④ 離婚経験者のリアルな体験談
実際に離婚を経験したママたちの声は、とてもリアルで力強いです。
以下は、筆者がヒアリングした体験談の一部です。
「ワンオペ育児で心がボロボロになって、ついに倒れた日、夫は“救急車呼べば?”って言ったんです。その瞬間、“もうこの人とは家族じゃない”と悟りました。」
「離婚してから、子どもがよく笑うようになりました。自分も精神的に落ち着いて、夜に泣かなくなったんです。離婚は終わりじゃなくて、新しい人生のスタートでした。」
「もちろん大変なこともあるけど、私は今、自分で自分の人生を生きてるって思える。子どもと一緒に前を向けるようになりました。」
こうした声を聞いていると、「離婚=不幸」という図式は、もはや時代遅れだと感じます。
もちろん離婚は簡単な決断ではありません。でも、「もう限界」と感じているママには、「あなたは間違ってない」と伝えたいです。離婚を考える自分を責めないでください。
何より、自分の人生をあきらめないでほしい。そのためにこの記事が、少しでも背中を押せるものになれば嬉しいです。
ーーーーとはいえ、離婚しないで関係を修復できたら、それに越したことはないですよね?
離婚を回避するためにできること【すぐできる3ステップ】

ワンオペ育児に限界を感じても、離婚を回避するためにできることは実はたくさんあります。
- 家事・育児の“見える化”をする
- 話し合いを“技術”として学ぶ
- 外部のサービスや支援に頼る
できることから、小さく始めてみましょう。
① 家事・育児の“見える化”をする
「夫は何もしてくれない」と感じているとき、実はお互いに“やってるつもり”になっているケースもあります。
まずは、家事・育児・労働を全て「見える化」するのがおすすめです。
例えば以下のように一覧にしてみると、自分がどれだけの負担を背負っていたのか、パートナーも自覚しやすくなります。
| 項目 | 誰がやっている? | 頻度 |
|---|---|---|
| 朝の準備(子ども・朝食) | 妻 | 毎日 |
| 保育園送迎 | 妻 | 平日 |
| 夜の寝かしつけ | 妻 | 毎日 |
| 休日の外出 | 夫 | たまに |
| 家計の管理 | 妻 | 常に |
| 晩ごはんの支度 | 妻 | 平日 |
数字やリストにすると、感情論ではなく事実ベースで話し合えるので、冷静な会話に繋がります。
「私ばっかり!」ではなく、「今の分担を一緒に見直したい」と伝えるだけで、相手の受け取り方も全然変わってきますよ。
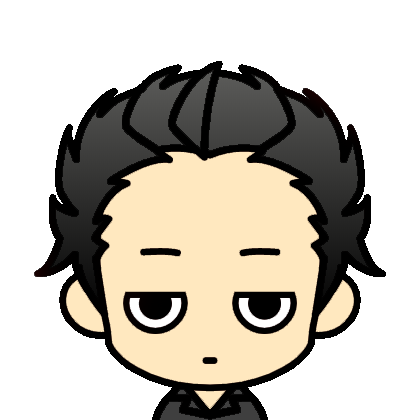
えっ…俺、何もやってないじゃん・・・
こんな感じで目に見える形にすると男性には効果抜群です!
② 話し合いを“技術”として学ぶ
夫婦の会話って、実は「感情」よりも「言い方」でこじれることが多いんです。
例えば、「どうしてやってくれないの?」という言い方だと、相手は防衛的になってしまいます。
それよりも、「私はこう感じてる」「こうしてもらえると助かる」と、自分の感情にフォーカスした伝え方が有効です。これを「アイメッセージ」と呼びます。
また、話し合いをスムーズにするには、以下のようなルールを設けるのも有効です。
- 相手を責めずに、自分の思いを話す
- 一度に全て伝えようとしない
- 相手の話を遮らず、最後まで聞く
- 議題を1つに絞る(例:「朝の分担」だけ)
こうした工夫をするだけで、「喧嘩ではなく対話」ができるようになります。

試してみてね♪
さらに、「感情」と「お金」の問題は切っても切り離せません。
話し合いをする前に、家庭の収支や支出項目を整理しておくことで、かなり冷静に話ができるようになります。
そこでおすすめなのが、ファイナンシャルプランナー(FP)に家計の状況を一緒に整理してもらうことです。
お金の不安があると、それだけで話し合いが攻撃的になりやすいので、第三者の視点でサポートしてもらえると安心ですね。

実際に我が家もお金の不安からケンカになることが多い・・・
最近は無料で相談できるFPサービスも増えているので、まずは気軽に家計の棚卸しから始めてみてはいかがでしょうか?
「離婚するかどうかより、今のお金の状況を整理すること」が、結果的に夫婦関係の再構築にもつながることは多いですよ。
③ 外部のサービスや支援に頼る
「夫が変わらないなら、自分がなんとかするしかない…」と、一人で抱え込んでしまうママは多いです。
でも、それはとても危険です。限界を超えてからでは、心も体もボロボロになってしまいます。

気付かないうちに限界を迎えてることも・・・
今は、家事代行・保育支援・自治体の相談窓口など、頼れる外部サービスがたくさんあります。
私は、「お金がかかるから…」と自分で頑張ろうとした結果、心と体を壊し仕事が続けられなくなりました。お金も健康も、夫婦関係も不安だらけという最悪の状態を迎えてやっと立ち止まりました。
あなたには私のような失敗はしてほしくありません。

だから、この記事を書いたよ。
健康だったらお金は何とかなります。まずは、自分を大切にしてください。
前述したFP相談は、金銭的な相談だけでなく、「別居したら家賃はどれくらい?」「ひとり親になった場合、もらえる支援制度はある?」といった、生活設計に関わる不安にも答えてくれます。
離婚前でも、別居を考えている段階でも、夫婦で一緒にがんばりたいと思っていても・・・どんな状態でもお金の不安がないだけで、心にゆとりが生まれます。だから、FPさんを味方につけてください。

なんでこんなにおすすめするかと言うと、私が救われたんだ。
お金の不安がなくなったらかなり気持ちが楽になったの。
以下に、よくあるお金の悩みと、FPがサポートできる例をまとめました。
| 悩み | FPができるサポート |
|---|---|
| 離婚したら生活できる? | シミュレーションと支出の最適化 |
| 別居後の家計が心配 | 予算設計と制度活用の提案 |
| 子どもにどれくらいお金がかかる? | 学費・将来設計の試算 |
| 養育費がもらえなかったら? | リスクを前提に家計を組む方法 |
頼ることは、弱さではなく「生き抜く力」です。
「まだ離婚は決めてないけど、今が苦しい」そんな人こそ、外部の力を使ってくださいね。
きっと今より楽に、そして前向きになれるヒントが見つかるはずです。
私もそうだったのですが、「今後の生活、本当に大丈夫かな?」という不安を感じたとき、FPさんに家計を見てもらったことで心がスッと軽くなりました。
たった30分話しただけで、「あ、これならやっていけるかも」って未来が見えたんです。

無料だから聞いてみるだけでもいいよね!

勧誘もないから安心してね♪
\ 家計の無料相談で未来を整える /
それでも離婚を選ぶ場合に知っておくべきこと

離婚を回避する努力をしても、それでも「もう限界」と感じることもあります。
- 離婚までの流れ(協議・調停・裁判)
- 子どものこと(親権・養育費・面会)
- 離婚後の生活費・支援制度について
- 離婚前にしておく“生活の準備”
未来の安心のために、冷静に準備をしていきましょう。
① 離婚までの流れ(協議・調停・裁判)
離婚には、大きく分けて「協議」「調停」「裁判」の3つの方法があります。
| 種類 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦間の話し合いで離婚に合意する | ◎費用がかからない ×合意できないと進まない |
| 調停離婚 | 家庭裁判所の調停員を交えて合意を目指す | ◎中立な意見が入る ×手間と時間がかかる |
| 裁判離婚 | 裁判で法的に離婚を争う | ◎最終的な決着がつく ×非常に時間・費用がかかる |
多くの場合、まずは協議離婚を目指します。
ただし、相手が話し合いに応じない、養育費や財産分与で揉めるなどの場合は、調停や裁判になる可能性もあります。
そのためにも、離婚を考えた段階で「どんな準備が必要か」「いつから動くべきか」を冷静に把握しておくことが大切です。
そして何より、“感情的な離婚”ではなく“生活を守る離婚”にすることが重要です。
② 子どものこと(親権・養育費・面会)
離婚の中で最も大きなテーマのひとつが、「子どものこと」です。
親権・養育費・面会交流について、事前にしっかり取り決めておかないと、後々トラブルになる可能性が高いです。
- 親権:どちらが取るか(原則として共同親権は離婚後は不可)
- 養育費:毎月いくら支払うのか/いつまで支払うか
- 面会交流:子どもともう一方の親が会う頻度・方法
養育費は、公正証書や調停などで正式に取り決めておくことが重要です。
しかし、実際は「口約束で終わってしまう」「途中で支払いが止まる」というケースが非常に多く、現実的には当てにできない状況もあります。
だからこそ、離婚後の家計は“養育費が無くても成り立つ”前提で設計しておくことが安心です。
それを可能にするのが、ファイナンシャルプランナー(FP)との家計シミュレーションです。
「養育費が途中で止まったら?」「習い事を続けさせられる?」「学費はどうする?」などの不安に、客観的にアドバイスしてくれます。
\ FPと一緒に「離婚後の生活」をシミュレーションしよう /
子どもを守るためにも、まずは親が経済的な見通しを立てておくことが第一歩です。
③ 離婚後の生活費・支援制度について
離婚後に最も直面する現実は「お金の問題」です。
専業主婦だった場合は特に、収入ゼロからのスタートになることもあり、経済的不安は非常に大きいです。
とはいえ、今の日本には多くの支援制度があります。以下は代表的なものです。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭に支給される生活支援金 |
| 就学援助制度 | 学用品・給食費などの援助 |
| 保育料の減免 | 所得に応じた軽減措置 |
| 住居確保給付金 | 家賃の一部を支給(条件あり) |
| 各自治体の母子支援 | 地域ごとに異なる支援あり |
「全部自分で調べるのはムリ…」という方は、FPに相談すれば、受けられる制度を一緒に洗い出してくれます。
制度の利用には申請が必要なので、事前に知っておくかどうかで大きな差が出ます。
「離婚後に慌てる」より、「離婚前に準備する」ことで、安心して新生活をスタートできます。
④ 離婚前にしておく“生活の準備”
「もう離婚する」と決めたときに、感情だけで動いてしまうのはNGです。
生活のための準備を、しっかり整えてから動くことがとても大切です。
準備しておきたいポイントは以下の通りです。
- 別居する場合の住まい探し(学区・保育園のことも考慮)
- 仕事・収入源の確保(扶養から外れる手続きも含む)
- 生活費のシミュレーション(養育費がない前提で)
- 公的支援制度の確認と申請準備
- 子どもへのケア・説明方法の整理
これを一人でやろうとすると本当に大変です。
でも、FP(ファイナンシャルプランナー)と一緒にやれば、家計のこと・制度のこと・教育費のことまで、一緒に整理できます。
しかも、今は無料で相談できるFPサービスもあり、スマホひとつで自宅から申し込めます。
\ 離婚前にお金の不安を全部スッキリさせよう /
子どもの未来のために、そして自分の人生のために。
今できることを、今日から始めていきましょう。
まとめ:ワンオペ育児と離婚をどう乗り越えるか

ここまで、ワンオペ育児の現実と離婚の可能性、そして回避する方法や準備について解説してきました。
- ワンオペ育児は心と体の限界を招く
- 離婚は“逃げ”ではなく“選択肢のひとつ”
- 決断の前に、必ず「お金の準備」を
- 一歩踏み出すあなたへ、最後に伝えたいこと
ここで、改めて振り返っていきましょう。
① ワンオペ育児は心と体の限界を招く
「誰も助けてくれない」「私ばっかり」──そんな日々が続くと、人は少しずつ心を失っていきます。
どんなに強いママでも、限界はあります。 だから、限界を迎える前に「助けを求める」ことは、立派な行動なのです。
誰かに頼ること。言葉にすること。 それだけで、少しだけ心が軽くなる瞬間がきっとあるはずです。
もし今、あなたがひとりで踏ん張っているのなら── まずは「自分のことを後回しにしないで」と自分に声をかけてあげてください。
② 離婚は“逃げ”ではなく“選択肢のひとつ”
離婚を選ぶことは、決して逃げではありません。
むしろ、「もうこのままではダメだ」と気づけたことは、自分自身と向き合った証です。
もちろん、離婚すれば全部が解決するわけではありません。 けれど、同じ場所にとどまり続けて「苦しみ続ける未来」ではなく、
「少しでも心が晴れるかもしれない未来」へ向かって動き出すことは、 あなたと子どもの人生を守るために、とても尊い選択だと思います。
大切なのは、「離婚する/しない」の2択ではなく、 「どう生きたいか」「どう暮らしたいか」を考えることです。
③ 決断の前に、必ず「お金の準備」を
離婚を決める前に、もっとも現実的に考えるべきなのが「お金」のことです。
生活費、教育費、家賃、医療費、養育費、手当…。 毎月の収支が見えていないままでは、離婚後の生活は非常に不安定になってしまいます。
逆に言えば、きちんと数字を“見える化”すれば、
「やっていけそうか」「どれくらい準備が必要か」など、現実的な判断ができるようになります。
そこでおすすめなのが、お金のプロ=ファイナンシャルプランナー(FP)との無料相談です。
FPは、収支の整理から、支援制度の確認、今後の生活設計まで、あなたの不安に寄り添って一緒に考えてくれる存在です。
\ 離婚する・しないに関わらず、今すぐお金を整える /
「お金の話って難しそう…」と思うかもしれませんが、 「一緒に整理してくれる人がいる」だけで、本当に心が軽くなりますよ。
④ 一歩踏み出すあなたへ、最後に伝えたいこと
ここまで読んでくださったあなたは、きっと今、人生の大きな選択に向き合っているのだと思います。
だからこそ、ひとつだけ、心からお伝えしたいことがあります。
あなたの選択は、間違っていません。
悩むことも、泣くことも、怒ることも、全部OKです。
でも、どうか、自分の気持ちをごまかさないでください。
そして、苦しみの中にいたとしても、「あなたはひとりじゃない」と知ってほしい。
このブログが、少しでもあなたの味方になれたなら── それだけで、書いた意味があります。
心から応援しています。未来は、変えていけます。
\お金のプロに無料で相談!/



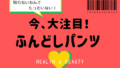
コメント